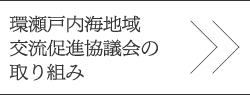2025.10.1
全国的な知名度を誇る「仁淀ブルー」で
初心者も挑戦できるリバーアクティビティ
透明な川に浮かんだ透明なカヤックが人気に

2013年、家業を継ぐために仁淀川町にUターンした古味雄也(こみよしなり)さんは、「まちが活力を失っている現状に愕然としました」と振り返る。人を呼び込み、関係人口を増やすことでまちを元気に…。そう考えた古味さんが着目したのは仁淀川。ちょうど帰郷の前年、NHKの番組で仁淀川が取り上げられ、その神秘的な美しさを表現した「仁淀ブルー」という言葉が認知され始めていた。可能性を見出した古味さんは、家業の建設業に従事しながら少しずつ準備を重ねて、2020年にクリスタルカヤックを用意し、仁淀川アウトドアセンターを立ち上げた。現在はクリスタルカヤック&SUP、カヌーに加えて冬場はこたつSUP、水上自転車など多彩な体験メニューを用意している。
古味さんが大切にしているのは、安全に楽しめるリバーアクティビティの提供。どの体験もしっかりと研修を受けたガイドが付く。また、体験の様子をドローンで撮影し、そのデータを利用者に提供するサービスも好評で、多い日には1日200人もの利用がある。「これからも川の自然とサービスのクオリティを守りながら、仁淀川町のファンを増やしたい」と意気込む古味さんだ。

- 冬は川の透明度がいっそう増す時期。そんな川の魅力をぬくぬくと味わえるのが、こたつSUP。飲食物の持ち込みも可能

- 更衣室やシャワー棟完備の店舗は仁淀川の最上流域。周辺は川の流れがゆるやかなので、初心者やお子さんも安心
仁淀川アウトドアセンター
住所/高知県吾川郡仁淀川町長屋6
TEL/0889-20-9619
営業時間/8:00〜17:00
定休日/年末年始(天候により臨時休業あり)
駐車場/あり
HP/https://niyodo.jp
※体験予約はホームページから受付、
クリスタルカヤック中学生以上6,900円〜、
SUP中学生以上6,000円〜
※時期により料金変動あり

鰹を知り尽くした高知県民も太鼓判!
「鰹乃國」の藁焼きは格別の味わい
太平洋を見下ろしながら高知ならではの豪快な体験

高知県民のソウルフードと言えば鰹のタタキ。なかでもこよなく愛されているのが、藁をくべた火で豪快に焼き上げる藁焼きだ。中土佐町久礼(くれ)地区は、400年以上前から鰹の一本釣り漁が行われている鰹のまち。一本釣り漁は、巻き網漁のように鰹に傷がつかないことに加えて、「久礼の漁船は日戻り漁(出港から24時間以内に帰港する)が主体。鰹の鮮度の良さも美味しさの秘密です」と説明するのは、「鰹乃國の湯宿 黒潮本陣」に併設された「黒潮工房」の山﨑正(やまざきただし)さん。黒潮工房では、そんな折り紙つきの鰹を、自分で藁焼きにする体験ができる。
鉄柵(てっさく)に載せた鰹の身を激しい藁の炎にあて、ごく短い時間で焼くことが美味しさの秘密。表面だけに火を通し、中身をレアに仕上げることで旨味を封じ込めるのだ。鰹は藁の香りを程よくまとい、食欲をそそる。太平洋を一望しながらの藁焼き体験、そして味わう本場の鰹のタタキは、忘れられない旅の思い出になるにちがいない。

-
(右上写真)体験によってできた鰹のタタキは、薬味とともにきれいに盛り付け。できたての味わいは格別(価格は時価)
(左写真)あまりの炎の激しさに腰が引けてしまうかも。目の前にはダイナミックな太平洋が広がる

- 手前が黒潮工房、奥に見えるのが鰹乃國の湯宿 黒潮本陣。立ち寄り入浴も可能だ
黒潮工房
住所/高知県高岡郡中土佐町久礼8009-11
TEL/0889-40-1160
営業時間/10:30〜13:30
定休日/第2木曜(祝日の場合は変更)
駐車場/あり
HP/http://honjin.or.jp/kobo.html
※体験は4〜10月の予約制(オフシーズンは食事、買い物に対応)。
体験予約はホームページ、電話で受付。
藁焼き体験は鰹代(時価)+800円

小さな鳴子に想いを込めながら
高知が最も熱くなる祭りを支える
新たな価値をプラスしたシン鳴子を続々と開発

「土産物の加工や卸販売の会社として、半世紀以上前に創業したのですが、1996年に工房を立ち上げ、鳴子の製造に軸足を置くようになりました」と話すのは、やまもも工房の公文佑典(くもんゆうすけ)さん。もともと鳴子とは、両面に取り付けたバチ(木片)が本体に当たって出る音により、田畑を荒らすスズメを追い払うための農具。よさこい祭りでは、これを手に持って踊るのが慣らいとなっている。「バチを片側だけにして装飾を施したり、多様なデザインを生み出したり。鳴子にデザイン性を持たせたのは私の父のアイデア」と公文さん。今や県内外の多くの人から、オリジナルデザインの鳴子の依頼が舞い込んできている。そもそも米の二期作発祥の地である高知では、米づくりに欠かせない鳴子が身近な存在であった。鳴子を通して高知の風土を伝えたいと、工房にはギャラリーを併設し、鳴子づくり体験も受け付けている。鳴子をモチーフにしたオリジナルグッズも豊富だ。
多くの観光客を惹きつけ、今や世界各地で人気を博しているよさこい。踊り子の手元には、公文さんらが心を込めてつくる鳴子が、存在感を放っている。

- 体験は9:00〜13:00に開催。所要時間は2〜3時間(10日前までに要予約)

- 1000本以上の鳴子が並ぶギャラリー。見学は1週間前までに要予約
やまもも工房
住所/高知県香美市土佐山田町佐古藪636
TEL/0887-52-4707
営業時間/9:00〜17:00
定休日/土・日曜
駐車場/あり
HP/https://www.yosakoinaruko.com
※見学・体験ともに要予約、鳴子づくり体験は2,500円

※駐車場ありには有料や提携、 近隣の公共駐車場も含まれます。